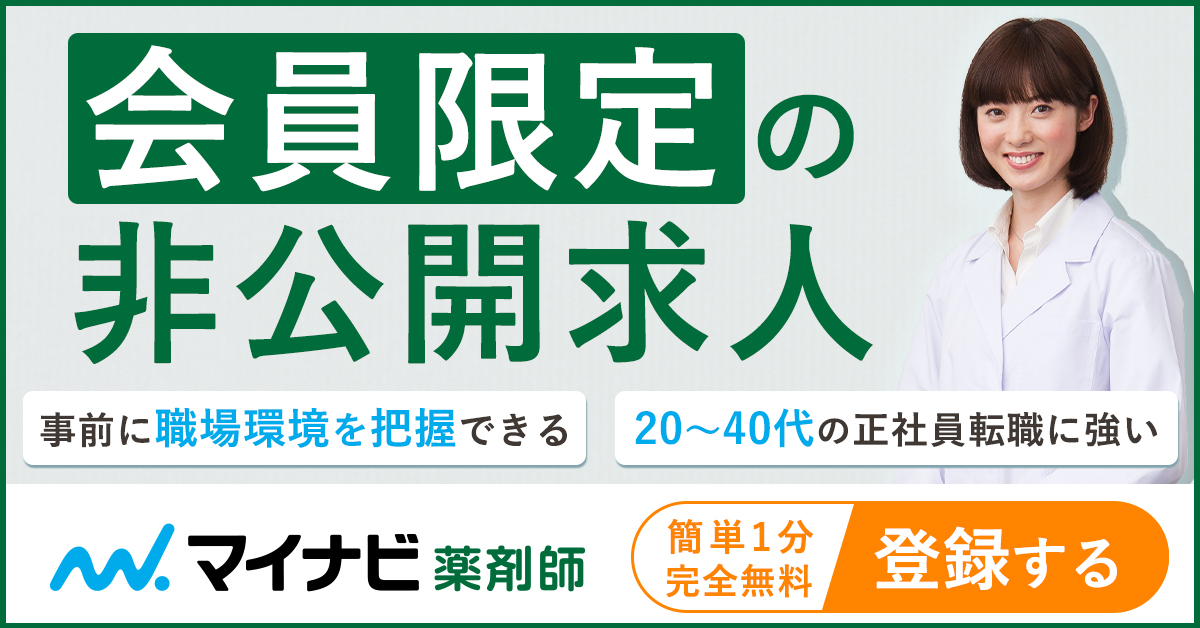![]()
こんにちは。Mr.Tです。
今回は五苓散についてです。
五苓散。
水分代謝の異常の改善に使われる漢方です。
低気圧による頭痛や二日酔いなどに使われます。
今回は五苓散について説明していきます。
| 薬剤師転職サイトおすすめ3選 |
|
あわせて読みたい
Contents
効能・効果
口渇、尿量減少するものの次の諸症 浮腫、ネフローゼ、二日酔、急性胃腸カタル、下痢、悪心、嘔吐、めまい、胃内停水、頭痛、尿毒症、暑気あたり、糖尿病
用法・用量
通常、成人1日7.5gを2〜3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。
なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
組成
本品7.5g中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス2.0gを含有する。
- 日局タクシャ:4.0g
- 日局ソウジュツ:3.0g
- 日局チョレイ:3.0g
- 日局ブクリョウ:3.0g
- 日局ケイヒ:1.5g
配合生薬の薬効
| 生薬名 | 読み | 効能・効果 |
| 桂皮 | ケイヒ | 芳香性健胃・発汗・解熱 |
| 蒼朮 | ソウジュツ | 健胃・利尿 |
| 沢瀉 | タクシャ | 浮腫・痰飲・清熱 |
| 茯苓 | ブクリョウ | 浮腫・健胃・痰飲・不眠 |
| 猪苓 | チョレイ | 水腫・膀胱炎・消炎 |
生薬の効能・効果一覧はこちらの記事から⇩
-

【生薬一覧】生薬の効能・効果について一覧にしてまとめてみた
もう少し各生薬の薬効を深く見ていきます。
桂皮
効能・効果
- 発汗解熱作用
- 血流改善作用
- 抗頭痛作用
- 抗動悸作用
蒼朮
効能・効果
- 止痢作用
- 筋肉・関節の止痛作用
沢瀉
効能・効果
- 利尿作用
- 消炎利尿作用
- 抗めまい作用
茯苓
効能・効果
- 利尿作用
- 抗めまい作用
- 抗動悸作用
- 鎮静作用
猪苓
効能・効果
- 利尿作用
- 消炎利尿作用
五苓散の処方構造
五苓散の構成生薬の構造は以下の通りです。
処方構造
- 水代謝異常改善作用:蒼朮-茯苓-猪苓-沢瀉
- 抗頭痛作用・抗動悸作用:桂皮
水代謝異常改善
蒼朮-茯苓-猪苓-沢瀉で水代謝異常を改善させます。
苓散は基本的には水代謝を改善する4つの生薬に、頭痛と動悸を改善する桂皮を組み合わせたものです。
五苓散の水代謝異常は水チャネルであるアクアポリン4(AQP4)の阻害作用を介したものです。
抗頭痛作用・抗動悸作用
桂皮により抗頭痛作用、抗動悸作用を示します。
こんな時にも使われる
航空中耳炎
飛行機が下がる時に気圧が変化して航空中耳炎が発症しますが、五苓散で予防できます。
飛行機が高度を下げる時に5g服用します。
下半身の症状にはあまり効かない
生薬には臓器特異性があるようで、桂皮が入った漢方は上半身の症状には効く傾向がありますが、下半身の症状には効果が出にくいようです。
下腿浮腫などには他の漢方を使います。
ノロウイルス
ウイルス性の腸炎の場合には下痢が水代謝異常になるので、下痢を止める効果もある五苓散をノロウイルスの時にも使用できます。
透析不均衡症候群
透析患者は強制的に体内の水分を取り除いているので、水代謝の異常、血圧の異常が起きています。
透析前に5g五苓散を服用すると、透析不均衡症候群は改善されます。
夏バテ
夏バテも水代謝異常なので五苓散が使われます。
まとめ
五苓散について解説しました。
五苓散はOTC(市販薬)でも販売されており、キャッチーな名称で販売されているのでなじみがある方が多いのではないでしょうか。
漢方はあまり効かないというイメージが強いため、二日酔い・低気圧による頭痛に効くと記載されているOTCが実は漢方だったと知ると、途端にあまり効かないのではないかと不安になる人も実際にいます。
五苓散のメインは水代謝の異常を改善させることです。
体内の70%は水で構成されています。
その水のバランスが崩れると様々な疾患が出てくる可能性があります。
気軽に使える漢方なので、体に不調がある時はぜひ使ってみてください。
薬剤師のオススメ転職サイト
ファルマスタッフ
![]()

ポイント
- 時給3,000円以上、年収600万円以上の高収入求人が豊富
- 日本調剤グループのノウハウを生かした充実の教育・研修制度
- 調剤薬局の求人に強い
- 派遣・パートにも対応
ファルマスタッフは高収入・好条件求人が多く、キャリアアップを目指したい薬剤師におすすめです。
公開求人数が40,000件以上で正社員はもちろん、派遣やパートにも対応しています。
また、調剤薬局の求人に強く、教育や研修制度が充実しているのも魅力です。
-



ファルマスタッフの評判や求人内容を徹底解説【薬剤師転職】
続きを見る
\初めての転職で使いたい薬剤師転職サイトNo.1/
業界トップクラスの求人数!マイナビ薬剤師
ポイント
- 転職サイト大手マイナビの運営により業界トップクラスの求人数
- 全国14ヶ所に拠点があり、地方でも対面面談が可能
- 薬剤師専任のキャリアアドバイザーが転職に関する悩みや不安を丁寧にヒアリング
- ドラッグストア・企業の求人に強い
転職サイトで有名なマイナビの薬剤師版です。
求人数が業界トップクラスで、薬剤師専任のキャリアアドバイザーが転職に関する悩みや不安を丁寧にヒアリングしてくれるので安心して転職活動を行うことができます。
-



マイナビ薬剤師の評判や求人内容を徹底解説【薬剤師転職】
続きを見る
\求人数No.1!転職と言えばマイナビ/
スピーディーな対応の薬キャリエージェント
![]()

ポイント
- 病院の求人に強い
- ママ薬剤師向けの検索可能ができる
- 迅速な対応でスムーズに転職可能
- 対面での面談が不要
日本の薬剤師の6割以上が登録しているm3.comのエムスリーグループが運営しています。
病院の求人に強く、対応がスムーズなので迅速に転職をすすめることができます。
-



薬キャリエージェントの評判や求人内容を徹底解説【薬剤師転職】
続きを見る
\薬剤師登録者数No.1/
あわせて読みたい
「医薬品」の関連記事
- 【2022年度版 処方日数制限一覧】 処方日数制限がある医薬品をまとめてみた
- 【クラバモックスの溶かし方】分包したら大惨事! 分包品のクラバモックスの調剤方法について
- 酢酸亜鉛の配合比率? 『亜鉛華軟膏』と『亜鉛華単軟膏』の違いについて徹底解説
- 【オグサワ処方】オーグメンチンとサワシリンの併用療法について徹底解説~なぜアモキシシリンが重複?~
- 【ボナロン経口ゼリー】噛んだり溶かしたらダメ? ボナロン経口ゼリーの飲み方について徹底解説

以下の記事もご覧ください。
参考文献:
- ツムラ五苓散添付文書
- 漢方薬処方レクチャー まずはこれだけ20
対象者
- 薬剤師などの医療人
- 登録販売者
- 漢方の知識を深めたい人
- 漢方初心者
代表的な漢方を20種類取り上げ、それぞれ一つずつを解剖して説明しています。
漢方に含まれる生薬を一つずつわかりやすく説明してくれ、生薬の組み合わせによってどのような効果が表れるかを説明してくれます。
個々の生薬の説明、生薬の組み合わせでの効果の発揮の仕方が非常にわかりやすい一冊となっています。
生薬の働きがわかれば、この本に取り上げられている20種類以外の漢方も何故この生薬が含まれていて、どのような効果があるのかがわかるようになってきます。
ココがポイント
- 代表的な漢方の20種類を説明
- 漢方初心者でもわかりやすい解説
- 陰陽などがわからなくても大丈夫
- 各生薬の働き、漢方の構造も詳しく説明