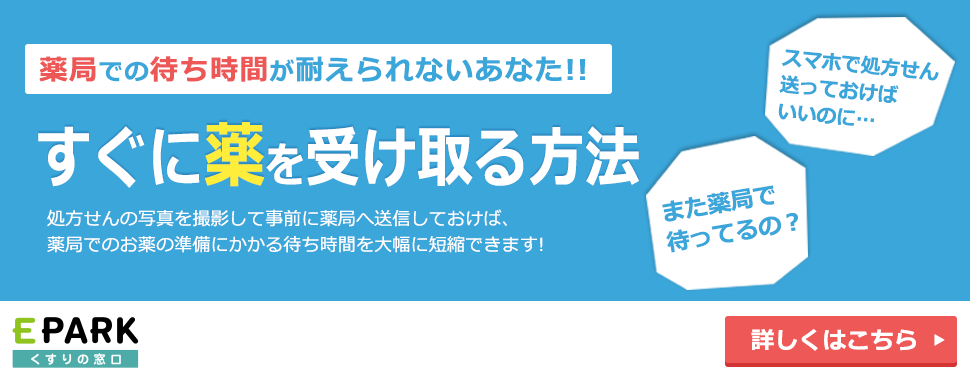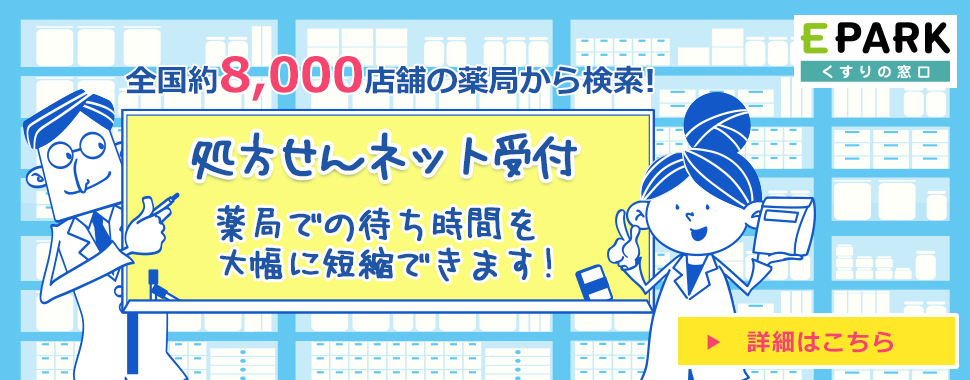![]()
薬局で薬をもらうときに薬剤師からも症状を聞かれるじゃん。
医師にもうしゃべってるし正直言いたくないんだけど。
薬の説明やその他の質問もうざく感じるときがあるんだよね。
気持ちはわかるんだけど、症状を改めて聞きなおすことによって、出された薬が本当に正しいかの確認にもなるんだ。
医師や事務が入力した内容が間違っていることも結構あるから薬剤師が確認したり、説明したりすることは患者さんの健康を守るために必要だと思ってほしいな。
こんな方におすすめ
- 薬剤師に症状を言いたくない人
- 薬剤師の説明がうざいと感じる人
薬局で薬をもらうときに薬剤師から症状を聞かれるのが嫌だったり、説明がうざいと感じる人は多いです。
「病院で医師に話したから薬剤師に再度話す必要はない」
「薬剤師に話して薬が変わるの?」
「疲れてるから早く帰りたい」
以上のように思っている人がほとんどなのではないでしょうか。
Mr.Tは薬剤師ですが、自分が患者の立場で薬をもらうときにもそう思うことがあるので、薬剤師の仕事を理解していない一般の人たちが嫌がるのは当然でしょう。
早く薬をもらって帰りたい気持ちはよくわかるのですが、薬剤師からの症状の聞き取りや説明には患者さんの健康を守るためにとても重要なことなのです。
以下に薬剤師が症状を聞いたり、患者さんに様々な質問をする理由を簡潔にまとめます。
ココがポイント
- 処方箋の記載ミスを防ぐ
- 処方薬が妥当かを判断
- 症状に合った薬が出ているかを判断
- 飲み合わせやアレルギーなどを判断
- 飲み忘れや副作用を判断
- 検査値などから処方薬が妥当かを判断
- 妊娠・授乳中などが医師に伝え忘れていないか確認
他にも様々な重要なポイントがあるのですが、簡単にまとめると以上のようになります。
以上のポイントを踏まえて今回は薬剤師に症状を言いたくない理由や説明がうざいと感じる理由、薬剤師が質問する意義を説明していきます。
\無料で使える/
Contents
薬剤師に症状を言いたくないときの対処法
![]()
この章では薬剤師に症状を言いたくないときの対処法について説明します。
風邪などで体調が悪く、あまり話したくない人やとにかく急いでいる人は以下の方法を使うといいでしょう。
しかし、言い方や態度、伝え方によっては薬剤師に悪い印象を与える可能性があるため、多用するのはお勧めしません。
正直に伝える
あまり話したくない、体調が悪い、急いでいるなどの理由を先に伝えてしまいましょう。
嫌がる患者さんを引き留めてまで長々と説明する薬剤師は少ないので、説明が始まる前に先に伝えておくと手短に説明を終えてくれるでしょう。
薬剤師はできるだけ詳細な情報を患者さんから聞き取りたいんだ。
でも、場合によっては最低限の情報だけ聞き取って終えることも多いよ。
飲んだことがあるので大丈夫
以前に飲んだことがあり、特に問題なかった場合は「飲んだことがあるので大丈夫、説明はいらない」などと伝えておきましょう。
飲んだことがないのに嘘をついたり、以前に気になる副作用が出た場合は危険なのでこの手は使わず、正直に薬剤師に話してください。
風邪とか整形、歯の痛み関係で以前と同じ薬が出されることはよくあるよね。
服用して問題なかった場合は説明は正直いらないと思うよ。
体調が安定しているから特に問題ない
血圧関係の薬など、継続で飲んでいて体調が安定している場合は「体調は安定している」ということを先に伝えてしまいましょう。
特に血圧関係の薬はしっかりと服用していれば血圧が安定し、体調や血圧の値があまり変わらない傾向があります。
最初に患者側から言ってしまえば薬剤師から「血圧の値は安定してますか」、「飲み忘れはありませんか」、「体調に変化はありませんか」などとたくさん質問されることを防げます。
体調や数値が安定しているということは、服用に問題がないと薬剤師は判断するんだ。
最初に患者さんから言ってもらえると薬剤師も色々なことを聞かなくていいから助かるよ。
コチラもチェック
-

血圧の数値が安定しない原因と正しい測り方について徹底解説
続きを見る
質問や特に不安に思っていることはない
自分は特に服用には困っていることはないと伝えるのも一つの手です。
継続している薬はもう慣れているので、説明や質問はもうこりごりだと思っている人は多いでしょう。
新規の薬などで嘘をつくのは危険なので絶対にダメですが、長年飲んでいる薬であれば正直に困っていることはないと伝えてしまってもいいでしょう。

同じ薬を何十年と継続しているベテランもいるから、そんな人に詳しい説明は必要ないよね。
嘘をついたり態度によってはブラックリストにのる
薬剤師も人間です。
患者さんに横柄な態度を取られると当然イラつきますし、トラブルを起こす患者は要注意のレッテルが貼られ、ブラックリストに追加されます。
Mr.Tが働いている薬局でもブラックリストが作成されており、要注意人物はスタッフ全員が気を付けるようにします。
医療は平等などといいますが、所詮人が行うことであり、感情が混じってきます。
薬剤師を見下しているような態度をとっている患者に丁寧な対応をしたいと思うでしょうか。
それでも丁寧な対応をするのがプロですし、ほとんどの薬剤師がプロの対応をしますが、中には適当な対応をする人もいますし、本当に困ったときに真摯に話を聞いてくれない可能性もあるということを頭にいれておきましょう。

自分が早く帰りたいからといって「飲んだことがある、説明はいらない」と噓をついて、家に帰ってから電話で色々と聞いてくる患者さんをどう思う?
ほとんどの人が自分勝手、自分のことしか考えてない患者だなと敬遠すると思うよ。
薬剤師の説明がうざいと思われる理由と意義
![]()

この章では薬剤師の説明がうざいと思われる理由と意義について説明します。
説明がうざいと思われる理由
ココがポイント
- 早く帰りたい
- 待たされて疲れている
- 同じことを聞かれるのが嫌
- 薬剤師に話して意味があるのか
病院で症状をしっかりと話し、長時間待たされて早く帰りたい気持ちはよくわかります。
薬局で同じことを話す意味がなく、何度も聞かれるのが嫌だと思う人が多いでしょう。
また、薬剤師は薬を袋に詰めて出すだけだと思っている人が多く、薬剤師の仕事が浸透していないこともうざいと思われる理由の一つだと考えられます。

職業への理解は正直難しいし、全員に理解してもらうのは難しいよ。
興味がない分野に耳を傾ける人はいないからね。
薬剤師が説明する意義
ココがポイント
- 処方箋の記載ミスを防ぐ
- 処方薬が妥当かを判断
- 症状に合った薬が出ているかを判断
- 飲み合わせやアレルギーなどを判断
- 飲み忘れや副作用を判断
- 検査値などから処方薬が妥当かを判断
- 妊娠・授乳中などが医師に伝え忘れていないか確認
うざいと思われている質問から、以上のような項目を薬剤師は判断しています。
まず、処方箋を入力する際にミスが生じる可能性があるので、患者さんに症状を再度確認する必要があるのです。
似たような名前の薬も多数あり、用法用量の記載ミスもたくさん起こります。
人間が入力しているので完ぺきとは言えず、医師や事務が間違えることも多いのです。
また、患者さんの現在の状態から処方薬が妥当か、副作用やアレルギー、医師に伝え忘れていることはないかなども確認し、もし不都合があった場合は疑義照会をして適切な薬に変更することもあるのです。
コチラもチェック
-



疑義照会の薬局でのポイントについて徹底解説【医師に怒られる?】
続きを見る
薬剤師の質問・説明から薬が変更になった例
![]()

この章では薬剤師の質問・説明から薬が変更になった例を挙げていきます。
薬の重複
A病院でムコスタを継続で飲んでいて、今回は整形外科でレバミピドという薬をもらった。
レバミピドはムコスタの一般名であり、まったく同じ薬なので併用する意味はなく、整形外科に疑義照会をして削除してもらった。

整形外科の医師に併用薬を伝え忘れたか、医師が見落としてた可能性があるね。
コチラもチェック
-



セルベックスとムコスタの違いについて徹底解説【胃薬・違い】
続きを見る
処方薬の間違い
「タチオン」が処方がされたが、患者さんは花粉症で飲むとのこと。
タチオンは中毒などに適応がある薬で、花粉症には適応がなく、おそらく「タリオン」の間違いだと推察。
疑義照会で入力ミスだということが発覚し、「タチオン」から「タリオン」に薬が変更に。

名前が似ているから誤って選択してしまったんだ。
これで患者さんが何も言わなかったらと思うとぞっとするね…
妊娠中の伝え忘れ
整形外科に行った女性が、NSAIDsの痛み止めを数種類もらってきた。
しかし、妊娠中だということを医師に伝えておらず、NSAIDsは妊娠中は禁忌。
疑義照会にてカロナールやNSAIDs以外の痛み止めに変更。

貼り薬とかでも妊娠中に使ってはいけないものもあるから注意が必要だよ。
医師が怖くてなかなか自分が言いたいことを言えない人もいるからね。
コチラもチェック
-



カロナールの使用期限の調べ方について徹底解説【検索方法】
続きを見る
腎機能の低下
腎機能が低下している患者さんに整形外科がロキソニンを処方。
腎機能については医師に何も話していなかった模様。
継続して当薬局にかかっている患者さんであり、腎機能の低下について把握していたことにより生じた事例。
結局、疑義照会にてカロナールに変更。

これも医師に伝え忘れの事例だね。
でも、医師から聞かれないと自分からは言わないよね。
痛み止めの関連記事
リクシアナの体重換算のミス
リクシアナは体重によって量が決まる薬。
引越しで病院を変えた際に、新しい病院にかかって継続でリクシアナを飲んでいると伝えた模様。
しかし引越し後に体重が落ちてしまい、本来飲む量より高用量のリクシアナが処方されてしまった。
現在の体重を疑義照会で医師に伝え、リクシアナ減量になった。

体重を確認せず、継続の薬をそのまま出してしまった可能性があるよ。
それかリクシアナの使い方を医師が知らなかったか。
上記の例以外にもたくさんの事例がありますが、薬剤師が行う説明や質問に意義があることが少しでもご理解いただけたでしょうか。
薬剤師が質問をしない、しっかりと仕事をしないと命に係わる可能性があるのです。
薬剤師からの説明がうざいと思うのは仕方がないことですが、上記のような事例を防ぐためにも一生懸命質問して患者さんの健康を守ろうとしていることをご理解いただければと思います。

特に飲んでいる薬が多い人や持病を持っている人は要注意なんだ。
薬がかぶる可能性や、適した薬が処方されていない可能性もあるんだよ。
処方箋に病名はなぜ記載されない?
![]()

この章では処方箋に病名がなぜ記載されないのかを説明します。
処方箋から症状を予想する
処方箋には患者さんの氏名や保険情報、処方された薬、医療機関の情報しか記載されていません。
患者さんの病名までは記載されていないのです。
「病名がわからないのに薬を出したり、指導したりするのか!」
と怒られそうですが、実際にはそうなのです。
出された薬からある程度病名は予測できますが、薬には様々な疾患に適応を持つものもあり、予測できないことも多いです。
なので、患者さんに質問し、自分が予想した病名と答え合わせをしています。
処方箋に病名が記載されない理由
薬剤師としては処方箋に病名を記載してもらえると助かります。
しかし、これは今のところ様々な問題があるので不可能です。
プライバシーの問題
人に自分の病名を知られたくない、医師があえて病名を伏せて薬を出しているなどがあります。
現在では患者さんに病名を告知することが多いですが、昔は正直に伝えないことが多かったのです。
例えば「がん」などは告知されたら精神的にかなりショックを受けてしまいますよね。
あえて患者さんには病名を伝えないで薬を出すということも多いのです。
病名が不確定
医師は神様ではありません。
わからないこともあるし、間違うこともあります。
1度の診察で病名を判断できないこともあるのです。
しかし、病名をつけないと薬を出すことができません。
可能性がありそうな病名をつけて薬を処方することもあります。
仮の病名をつけないとレセプトを送れないので。
*レセプトとは、医療機関が保険者(市町村や健康保険組合)に請求する医療報酬の明細書のこと。
「病名わからないけど薬は出します。」は、通用しないですよね。
適応外処方
適応外処方とは、承認されている効能・効果以外の目的で使用する処方です。
適応外処方はたくさんあります。
例として、シメチジンは胃酸の分泌を抑える胃薬に分類されますが、適応外処方で肩関節の石灰沈着性腱板炎という肩に激しい痛みを起こす疾患に使われる事があります。
レセプトに石灰沈着性腱板炎と記載してシメチジンを出すことはできません。
あくまでもレセプトに記載できるのは適応内、承認されているものだけです。
なので、処方箋に適応外処方の病名を記載するのもマズイですよね。

薬局側としては、一応病院に確認しておいた方が返戻を防げるよ。
まとめ
![]()

今回は薬剤師に症状を言いたくない理由や説明がうざいと感じる理由、薬剤師が質問する意義について説明してきました。
最後にもう一度ポイントをまとめます。
ココがポイント
- 処方箋の記載ミスを防ぐ
- 処方薬が妥当かを判断
- 症状に合った薬が出ているかを判断
- 飲み合わせやアレルギーなどを判断
- 飲み忘れや副作用を判断
- 検査値などから処方薬が妥当かを判断
- 妊娠・授乳中などが医師に伝え忘れていないか確認
薬剤師からの質問がうざい、煩わしいと感じる気持ちはよくわかりますし、薬剤師側も理解しています。
しかし、患者さんの健康を守るためには説明や質問をしないとどうしてもわからないこともあるのです。
よく喋ってくれる患者さんは薬剤師に好かれますし、横柄な態度をとる患者さんは嫌われます(喋りすぎて業務に支障が出る患者さんは別ですが…)。
これは人間対人間なのでどうすることもできません。
スムーズに事が進めば3分~5分程度で薬の説明は終わるので、薬剤師、薬局といい関係を築くためにも薬剤師からの質問に少しでも答えるようにすると、いざ困ったときに薬剤師が全力で手助けしてくれるようになるでしょう。

人間関係を悪化させていいことなんて一つもないよ。
困ったときはその分野のプロに聞くのが一番確実だしね。
中途半端な知識ほど厄介なものはないよ。
薬局での待ち時間を減らしたい人へ
「EPARKくすりの窓口」は、調剤薬局に行く前にスマホから受付することで、薬局で長時間待つことなく薬を受取ることのできるサービスです。
全国18,000店舗以上の薬局・ドラッグストアで利用でき、自宅や会社近くの都合の良い薬局で好きな時間に薬を受け取ることができるため、時間の節約や二次感染の予防につながります。
家の近くの薬局でもらいたい、子どもがいるから早く帰りたいなど、薬局での待ち時間を減らしたい人におすすめのアプリです。
\ダウンロード・登録は無料/
「薬局・薬剤師」の関連記事
- 【力価・計算】力価って何? 計算が苦手な薬剤師に計算方法を徹底解説
- 【経過措置】薬のクビ宣告? 経過措置になった薬の対処法について徹底解説
- 【不足薬・対応】薬局に在庫が無い場合はどうする? 医薬品が不足したときの対応方法について徹底解説
- 薬剤師の仕事は誰にもできる? 自称専門家たちについての個人的見解
- 【処方箋・略語一覧】v.d.S.? v.d.E.? 処方箋の略語を一覧にしてまとめてみた